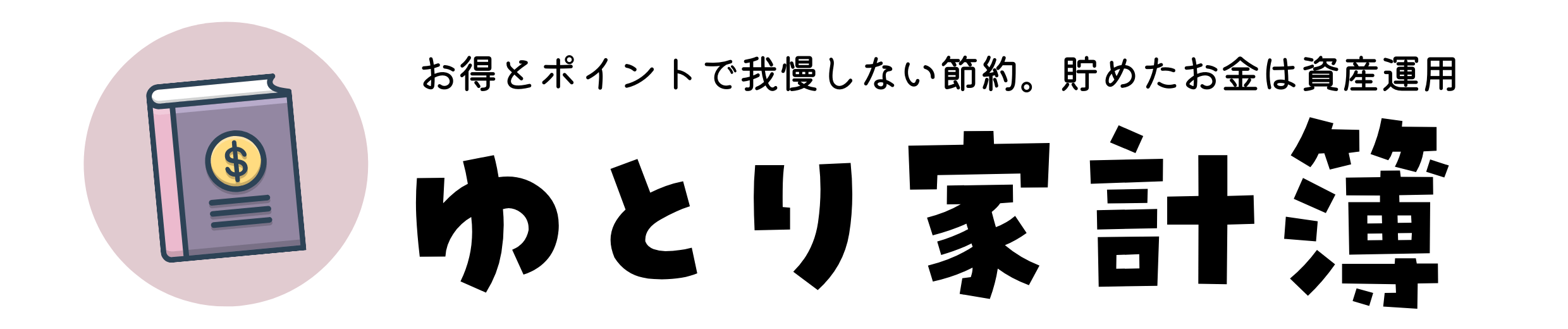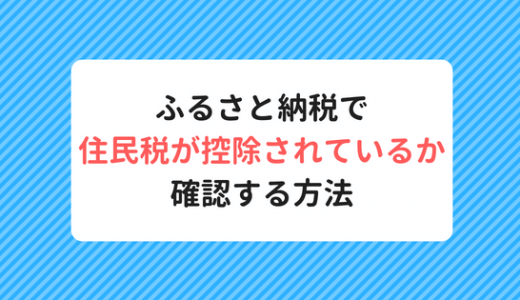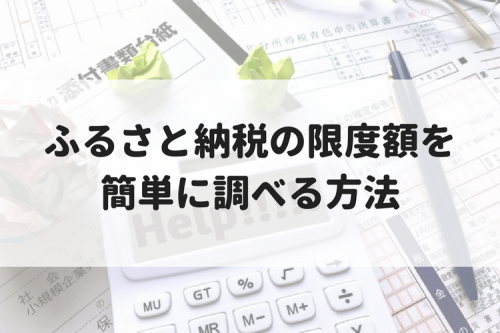[box class=”box32″ title=”ふるさと納税の記事”]
[/box]
今では手軽に出来る節税対策として有名になっているふるさと納税
今まで収入も多くなかったので、支払う税金も少なく節税対策とか考えたこともなかったけど
世帯年収500万になることがわかってから税金の計算をすると、思ったより高かったので
気になりだしたふるさと納税
でも、ふるさと納税のしくみが分からずなんとなく2000円で返礼品が貰えるしか知らなかったので
利用する事に躊躇していましたが調べていくうちに手軽にできる節税対策だと思い
2016年、2017年とふるさと納税を利用し節税対策に成功。
[say name=”みつ子” img=”https://chamilog.com/wp-content/uploads/2018/09/icon4.png”]節税対策は気になっているけど、分からない[/say]
そんな方に、この記事では分かりやすくふるさと納税のしくみと注意点を解説
ふるさと納税って何?
ふるさと納税とは、自分が好きな自治体や応援したい自治体にお金を寄付をすることです。
自治体へ寄付したお金は子育て支援や街の活性化、災害時などの支援にも役立てられます。
返礼品が貰える
自治体によっては寄付したお金を何に使って欲しいか選べる自治体もあり
寄付したわたしたちは、自治体が用意しているお礼の品(返礼品)を貰うことができます。
ふるさと納税のしくみ
分かりやすく言えば住民税と所得税が安くなる
自治体へお金を寄付するとお礼の品が貰えるだけではなく、わたしたちが支払うべき住民税と所得税が安くなり
実質自己負担額が2000円でふるさと納税の寄付をすることができます。
細かく言えば安くなるという言い方は違うけど。分かりやすく言うと安くなります。
例えばふるさと納税の寄付を10000円した場合
10000円(寄附金額)-2000円=8000円
この8000円が本来支払いする所得税と住民税から差し引かれます。
ふるさと納税は節税ではない?
税金の話で難しくなるので分からなければ飛ばしてOKです!
ふるさと納税は分かりやすく言うと住民税や所得税が安くなると言いましたが
細かく言えば節税というよりかは本来支払うべき税金を前払いして返礼品を貰い
後で所得税や住民税から前払いした分を差し引かれているのでお得に税金が支払えるという事になります。
節税ということにしっくりこない方は、お得に税金が支払えると思ったほうが分かりやすいかもしれません。
寄付金には限度額ある
自己負担2000円だったら沢山寄付をすれば、住民税も0円になるんじゃないの?
と思うかもしれませんが、うまくできているのでそんなわけありませんw
ふるさと納税には限度額があります。
限度額は年収や家族構成によってきまる
限度額は年収によって決まりますが、さらに細かく言うと家族構成によっても変わります。
「年収400万の一人暮らし」と「年収400万で家族4人暮らし」では、限度額も変わります。
限度額の早見表
[mobile]横にスクロールしてネ[/mobile]
| ↓年収 | 独身 又は 共働き | 夫婦 又は 共働き + 子1人(高校生) | 共働き + 子1人(大学生) | 夫婦 + 子1人(高校生) | 共働き + 子2人(大学生と高校生) | 夫婦 + 子2人(大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
| 675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
限度額の調べ方
ふるさと納税の限度額は前年度の年収ではなく、ふるさと納税をする年の年収によって決まります。
2018年にふるさと納税する限度額は、2018年の年収によって決まります。
でも、2018年ってまだ終わってないから2018年にいくら稼ぐかなんてわからないですよね?
その為、2018年の年収を予想してふるさと納税の限度額を調べないといけないのです。
早見表を使うと、大まかなふるさと納税の限度額を簡単に調べることができるけど、
融通が利かないので、わたしは限度額を確認できるツールを使って調べてます。
詳細は「ふるさと納税の限度額を簡単により正確に調べる方法」で説明中
[kanren id=”861″]
限度額を超えるとどうなるの?
限度額を超えてしまうと、自己負担2000円にプラスで限度額を超えてしまった金額がかかります。
例えばふるさと納税の限度額が25000円なのに30000円寄付してしまった場合
自己負担2000円+5000円=合計7000円の自己負担になってしまうので、損をしてしまいます。
その為、限度額ギリギリまで寄付をせずに、少し余裕を持たせて寄付することがオススメ。
ふるさと納税を申し込み(自治体へ寄付)する方法
自治体へ寄付する方法は、ネットから手軽に寄付をすることができ
直接自治体のHPからも寄付ができますが、他にも
お得にするなら楽天市場
わたしも2016年からふるさと納税を始めましたが、楽天ポイントも貯まるし、楽天ポイントも使えるし
楽天市場のふるさと納税をずっと利用してます。
[kanren id=”2757″]
ふるさと納税で寄付をした後は申告が必要
寄付をするだけでは、返礼品をもらえますが、税金は安くなりません。
確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用し、寄付をした申告をしないといけません。
今までは、ふるさと納税をすると確定申告が必要でしたが、ワンストップ特例制度ができ
手軽にふるさと納税を利用する事ができるようになりました。
ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税を行う場合、その年の1年間で寄附先が5つの自治体までなら確定申告をせずに税金の控除が受けられるという制度
ただし、ワンストップ特例制度を使用する際、条件があり
[box class=”box26″ title=”条件”]
- 確定申告が不要な給与所得者(医療費控除などをする人は除外)
- 1年間で寄附先が5つの自治体まで(寄附先が5つなので極端な話1つの自治体に6回寄附しても1つの自治体としてカウント)
- 申請用紙の提出が必要
[/box]
わたしは、医療費控除があったので、ワンストップ特例制度は利用せず、確定申告をしていましたが
2018年は医療費控除がないので、確定申告より楽にできるワンストップ特例制度を利用する予定です。
ふるさと納税にチャレンジ
[box class=”box32″ title=”まとめ”]
- 自治体に自己負担2000円で寄付ができて、返礼品が貰える
- 住民税や所得税が安くなる
- 寄付金額には限度額がある
- 限度額を超えると自己負担2000円以上かかる場合がある
- ふるさと納税を利用したらワンストップ特例、もしくは確定申告で申告が必要
[/box]
わたしたちにとって、ふるさと納税は返礼品が貰えたり節税にもなりますが
自治体へ寄附をできるというwin-winな感じが魅力的なのでオススメの節税対策です!
ぜひ、ふるさと納税にチャレンジしてみてください!
続いては、ふるさと納税する際の限度額を知ろう!で限度額を解説中
[card2 id=”861″]